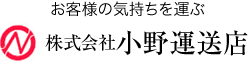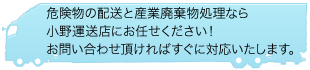創業者小野為吉
株式会社小野運送店の創業者・小野為吉は、愛知県碧海郡桜井村に生まれた。桜井村は愛知県のほぼ中央の村で、現在は安城市に編入されている。生家は農家であったという。
為吉は野心家であった。小さな山奥の村で生涯百姓をして暮らすことなど我慢がならなかった。東京に強い憧れを抱いていた為吉は一旗揚げようと、明治時代の初めに上京する。しかし、東京にこれといったつてがあるわけでもなかった。ようやくたどり着いた先が南品川であった。当時の地名は東京府荏原郡東海寺。戦前からこの地に暮らしているお年寄りは、今もこの界隈を東海寺と呼ぶ。
京浜急行の新馬場駅から小野運送店本社へ向かう道筋にある東海寺は、江戸時代きっての名刹で、1638(寛永15)年、3代将軍徳川家光が沢庵和尚のために建てた寺として知られている。広大な寺域を有し、家光以降の歴代将軍が鷹狩りの際に頻繁に訪れたと伝えられている。小野為吉はここで、土木建築業の会社の世話になる。
土木建築業には資材の運搬がつきものである。当時の陸上輸送の主力は馬で、馬力で荷車を引いていた。農家の出身で馬の扱いに慣れていた為吉は、頑健な身体で建設作業をこなすとともに、馬方としても重宝されたと考えられる。為吉は田舎者には珍しく、弁舌が立ち字も上手だった。陽気でひょうきん者でもあったため、親方に気に入られ、しばらくすると番頭格として一目置かれる存在となった。
為吉の写真は残っていないし、小野家の存命の人間で彼と話をした者はいない。何せ、小野運送店の開業は今から120年も前の話である。大政奉還を経て、1868(慶応4、明治元)年の江戸城明け渡し、徳川最後の将軍・15代徳川慶喜の蟄居により江戸時代が終わるが、そこからまだ28年しか経っていない大昔である。小野為吉は暗殺された坂本龍馬(1836~1867)や、西郷隆盛(1828~1877)、勝海舟(1823~1899)など維新の英雄たちと、ほぼ同じ時代を生きていたことになる。
馬力屋稼業
自動車の歴史をひもといてみよう。初めて海外から日本に自動車が持ち込まれたのは1898(明治31)年。後述するように小野運送店が開業したのは1896(明治29)年だから、その頃まだ日本には1台の自動車もなかったことになる。国産自動車の生産が始まったのはそれから30年以上を経た1930年代のこと。日産の設立が1932(昭和7)年、トヨタが1933(昭和8)年であったことから分かるように、乗用車やトラックが日常的な陸上輸送の手段として定着したのは、太平洋戦争以降と考えてよいだろう。
鉄道や海上輸送を除けば、自動車が普及するまで、長い距離の荷物運送は主に馬によって行われていた。荷車や台車に荷物を乗せ、それを馬が引いて運ぶ──つまりは「馬力」に委ねられていた。それゆえ、当時の運送業者は一般に“馬力屋”と呼ばれ、馬力屋には馬の扱いに長けた馬方が大勢雇われていた。
馬力屋の実態を知るのに格好の資料がある。それが石井常雄著『「馬力」の運送史(トラック運送の先駆を旅する)』(2001,白桃書房刊)である。著者は交通論の専門家であり、生家が戦前池袋で馬力運送を営んでいたことから馬力屋の実態に非常に詳しい。
本書によると、1931(昭和6)年、東京全域で1万8,170台の荷牛馬車が貨物運送に従事していたという。
「戦時中の1941(昭和16)年には、都内に936業者、2,014台の荷牛馬車が活躍しており、この時期、全国に15万9,334業者が17万8,718台の荷牛馬車を使って、輸送の一環を支えていた。」とある。
このように、一般的な陸上運送の主役であった馬が、その座をトラックに譲ったのは太平洋戦争の後のことで、戦前・戦中を通じて運送業の土台を支えてきたのは馬力屋であった。その証拠に、今でもエンジン出力の単位には「馬力(75kgの物を毎秒1m動かす力)」が使われている。
小野運送店を創業
1896(明治29)年2月、小野為吉は独立し、馬20頭を擁して馬力運送業を起こした。働きぶりが認められ、暖簾分けするかたちでの起業であった。ここに120年に及ぶ小野運送店の歴史が始まる。
ところで、為吉はどんな人物だったのだろうか──。為吉の孫に当たり、昭和後期から四半世紀にわたり社長を務めた小野為男(5代目)は、「非常に弁舌が立つ一方、品川の宿場町ではひょうきん者で名の知れた存在だった」と聞いたことがあると言う。荒くれ者も多かったであろう当時の土木建築業仲間の中ですぐに頭角を現したところを見ると、腕力・膂力のみならず頭もよく、人の上に立つ器量を備えていたと思われる。
また、3代目社長・小野昌邦夫人の小野トシはこう言う。
「車夫馬丁と言われたように、身分的にもかなり低い位置にありながら、人の何倍も働いて一代で財を成したと聞いています。身体が大きく力が強く、特に目黒川の改修工事で人の何倍も働いてたくさんの賃金を得たといいます。昔から住み込んでいた番頭さん夫婦の話では、品川区では“東海寺の小野”といえば知らない者はないくらいの金持ちだったとか。私が嫁いできたときも馬は13頭いましたが、戦前は40~50頭いたそうです。」
新馬場の目と鼻の先に品川神社がある。品川神社は北品川の鎮守で、北の天王様として人々に親しまれている。江戸時代には北品川稲荷社、品川大明神、天王社と呼ばれた。鎌倉時代の初め、1187(文治3)年、源頼朝が安房国洲崎大明神を勧請したと伝えられるこの由緒ある神社の氏子総代を、よそ者の為吉が務めたという事実からも、その立身出世ぶりがうかがえる。
ちなみに、品川神社の総代は代々小野家が引き継いでいる。為吉、貞義(2代目)、為男(5代目)、そして現社長の正彦(7代目)と続いている。境内に今も鎮座する狛犬は、1925(大正14)年、為男の誕生を記念して貞義が献上したものである。現在の社殿は1964(昭和39)年に新築された。こうした話から、小野運送店は馬力運送業として手広い商いをし、資産を蓄え、品川界隈では一・二を争う馬力屋であったことがうかがえる。 このほかにも、埼玉県東松山市の寺社に東京・馬力運送の碑が建っている。銅板で、その中に荏原郡品川・小野為吉の名前が記されている。
“中興の祖” 小野貞義
1919(大正8)年、為吉は創業から四半世紀を経て順風満帆の経営状況にあった小野運送店の経営を、2代目の貞義に託した。
貞義は為吉の実子ではない。生涯子宝に恵まれなかった為吉は、自ら興し軌道に乗せた事業を、最も近い親族の男子に継がせたのである。戸籍上は為吉の長男となっているが、実は弟・小野梅吉の子。為吉にとっては甥に当たる。
それから6年後の1925(大正14)年、為吉は生涯の幕を閉じた。愛知県の片田舎から上京し、馬力屋稼業を一代で興し財をなしたのだから、悔いのない成功者の人生を歩んだといえよう。
貞義は、為吉は対照的に三男三女をもうけた。しかし、その妻は産後の肥立ちが悪く、6人目を生んでしばらくして息を引き取った。再婚した貞義は、その妻との間に6人(男5、女1)の子をもうけた。その当時にしてもかなりの子だくさんであった。その昌邦は4代目、為男は5代目となり、為男の息子の正彦は現・7代目社長を務めている。
為吉の後を継いだ貞義は、歴代社長の中でも最長の半世紀にわたり社業を牽引し、小野運送店の経営基盤を構築した最大の功労者である。それだけでなく、今日に至る小野家の大家族の血統をつくり、小野運送店120年の歴史の存続に寄与した功績は大きい。
貞義は、馬力運送業を営む上で非常に重要な素質を備えていた。それは「馬」に精通していたことである。貞義は日露戦争の後、騎兵隊として徴用された経歴を持つ。騎兵は乗馬・徒歩いずれもの戦闘をこなす。為吉がここに着目し、いずれは後継者にと考えていたことは容易に想像できる。貞義は習志野の騎兵隊駐屯地に立ち寄る際、東京まで足を伸ばし小野運送店の叔父のもとによく顔を出した。それが縁で小野家の養子になった。
「とにかく馬が好きだった。荷車を引かせる馬を調達するために、よく北海道まで足を運んでいた。いい馬を見つけるとその場で購入し、2歳の頃に栃木県の岩船山辺りの農家に、タダでいいから畑仕事に使ってくれと預けた。そして、重労働に耐える足腰が備わった4歳になると家に連れてきた。馬を世話した人が一緒にやってきて、そのまま馬方として働くケースも多かったね」と、5代目・小野為男(貞義三男)は父の思い出を語る。
前述の『「馬力」の運送史』の中で、著者は馬力運送業開業に際しての必須条件として、「輓馬の性格・能力を把握し、健康で長く使用できる飼育と管理が、事業維持にとって重要である。(中略)そのために、業者や馬夫(馬方)は、輓馬への細心の注意が発揮できるカンとコツを取得しておかねばならない」と述べている。そういう意味においても、為吉はまたとない後継者を得ることができたのである。
貞義は、それから3代目の小野慶十(貞義の弟)に経営のバトンを託するまで、実に50年にわたり社長を務めた。初代が生み育て土台を築いた小野運送店を受け継ぎ、日中戦争から太平洋戦争に至る戦乱の時代を乗り切った。さらには、仕事量が減った戦後の混乱期をしのぎ、馬力運送からトラック運送へ、運送業の大きな構造転換の時期にも、時代に乗り遅れることなく社業の存続を図り今日の安定経営の基礎をつくった。
為吉が創業者なら、貞義は“中興の祖”である。今日の近代的な当社の営業基盤は、2代目小野貞義の時代に築かれたといえよう。
都会の真ん中に農家がある
ところで、戦前の小野運送店のたたずまいはどんなものだったのか。昔は旧東海道から海側は見渡す限りの湿原であったという。そこをどんどん埋め立てて陸地を広げ、中小工場を建て、品川は工業地帯に変貌していった。
小野運送店の本社所在地は品川区南品川4丁目。昔も今も変わらない。京浜急行の新馬場駅から第一京浜国道を渡り、5分ほど歩いたところにある。戦前の店の写真はほとんど残っていないが、それは店というよりも地方によく見られる大農家のようであったと思われる。
多いときは50頭もいたという馬を収容する馬小屋、馬方が寝泊まりする宿舎、そして小野家の家族が住まう住居を含む当社の敷地は広大で、この界隈ではひときわ偉容を誇っていた。
「こんな農家みたいな家が都会のど真ん中にあることに、本当に驚きました。北海道の大農家に嫁にきた感覚でしたね。私が嫁いだ当時、馬は大分減ったようでもまだ13頭いて、1頭の馬に1人ずつ馬方がいた。地方から働きにきた馬方たちが近くの宿舎に寝泊まりし、住み込みで働いていました」と小野トシが語る。
母屋となる家はものすごい豪邸だったそうだが、強制疎開で壊されてすでになかった。小野トシが続ける。
「義父(貞義)は公営競馬(大井競馬)始まって以来の馬主で、馬主会の副会長をしていたこともあり、多いときには競走馬が8頭くらいいました。豚小屋も20くらいあって、馬小屋・豚小屋の掃除が私の日課になっていました。門前のお稲荷さんのところに専属のかじ屋がいて、馬の蹄鉄をつくっていましたね。洗濯物を干すのに、ウチでは洗濯バサミ代わりに蹄鉄を使っていたんです。」
こうした証言から、当時の馬力屋の様子が伝わってくる。小野運送店に限らず、生き物の馬が主役の馬力運送業はどこも同じようだったと考えられる。
深まる戦時色と交通統制
馬力運送業として起業した小野運送店は、明治天皇が崩御した1912(明治45・大正元)年には創業16年を迎えていた。
ここから始まる大正時代の15年間と、日中戦争が始まる前の1935(昭和10)年頃までの期間が小野運送店の成長期に当たり、馬力屋として最盛期を迎えていたと考えられる。
しかし、どんな事業にも盛衰がある。このまま順調に伸びていこうとしたとき、企業努力では超えられない大きな壁に前途を遮られた。戦時体制への移行に伴う交通統制であった。
1938(昭和13)年、国は戦時体制の先駆けとなる一つの交通統制策を打ち出した。それが「陸上交通事業調整法」の施行である。日中戦争が始まり、戦時体制への移行を余儀なくされる中、都市部での交通機関の統制を強めると同時に乱立する業者の過剰な競争を避ける目的で、鉄道・バス会社の整理統合を実施したのである。
トラックにおいては、市町村単位から都道府県単位に会社の一本化が進められていった。小運送(鉄道で運ぶ貨物の集配・積み卸しを行う業務)においては、1937(昭和12)年9月に「日本通運株式会社法」が制定(1950〈昭和25〉年に廃止)された。同法の狙いは、戦時中の経済統制の一環として、戦時物資を円滑に供給することにあった。
そのため、トラックを用いた鉄道貨物の集荷・配達業務を行う全国の通運業者は統合され、国策により設けられた日本通運株式会社(日通の歴史はここに始まる)のもとで業務を行うよう、規制されたのである。
物心ついた頃から父・貞義に運送業をたたき込まれたという小野家五男、小野晃(現・相談役)は言う。
「学校から帰ってくるとよく馬の世話をさせられた。兄貴2人(昌邦、為男)には家の手伝いをさせなかったところを見ると、親父は私に家業を継がせる気だったと思う。小学校6年で疎開先(為吉の故郷・愛知県碧海郡桜井村)から帰って来たころは、当時停車場(ていしゃば)と呼ばれた品川駅の荷扱いによく連れていかれた。荷出し場には日本ペイントのペンキをつくる材料の粉であるタンカルなどの袋がたくさん積まれていて、20kgくらいの袋を担いで馬の引く荷馬車に積んだ。目黒川を船で運んで来るものもあって、船に渡した細い板の上を担いで渡った記憶もある。」
このように、品川駅の荷扱いで地域の小運送業者としての地盤を確立していた小野運送店にとって、戦時体制下の国策とはいえ、日本通運株式会社法の施行は大きな打撃であった。
合同運送時代
その後も戦時色はさらに強まり、日本通運に運送業を集約させる交通統制は続く。1941(昭和16)年12月、日本がハワイの真珠湾を奇襲したことで、ついに米国、英国などの連合国を相手とした太平洋戦争の火蓋が切られた。日中戦争により撒かれた火種は、こうして最悪のかたちで日本を戦禍に巻き込んだのである。
日中戦争の拡大に伴い、すでに1938(昭和13)年には国家総動員法が制定されていた。国防目的達成のため、あらゆる人的および物的資源を統制運用する大幅な権限が政府に与えられたのである。
太平洋戦争の最中は、戦時経済統制ならびに軍需産業の支援を目的に、産業界全般で「企業合同」が行われた。運送業も例外ではなく、それまで各駅において過当競争を繰り広げてきた地域の運送会社を一つの合同会社に統合する政策(合同運送)が推し進められた。
地域に根を張って地道に営業を続けてきた中小運送会社は、どこも皆この決定に納得がいかなかった。「戦時中とはいえ、国防のためとはいえ、あまりに横暴ではないか…」というのが偽らざる心境であり、これを受容するのにはかなりの忍耐が必要だった。
貞義も苦渋の選択を迫られたが、なかなか首を縦に振ろうとしなかったため、品川警察署に連行されるという一幕もあったという。
しかし、最終的には従うほかはなく、当社は1941(昭和16)年に「統合会社大崎運送」として、1945(昭和20)年にはさらに「統合会社品川運送」として営業を続けることになった。
こうして政府の統合政策のもと、全国主要都市にできた地区合同運送会社は、さらに戦局が悪化し陸運統制令が改正・強化されると、最終的には日本通運の一元管理化に入る政策が推進されていった。統合会社のもとでの営業は終戦後もしばらく続き、1947(昭和22)年にようやく解散。小野運送店は同年7月29日、資本金19万円で晴れて戦後のスタートを切ったのである。
馬力からトラックへ
創業120周年の年輪を重ねた小野運送店の歴史は、終戦(1945(昭和20)年)を境に、大きく前半の50年、後半の70年に分けて考えることができる。
政治・経済・社会が戦争を境に大きく変貌を遂げたように、運送業も戦前と戦後では大きくその姿を変えた。戦前は同じ運送業でも、馬を運送手段とする「馬力運送業」であった。しかし、戦後は、トラックの急速な普及により、運送業は自動車による「トラック運送業」に大きく変貌を遂げたのである。
馬からトラックへと簡単にいうが、事業者にとってそれは経営の根幹に関わる大問題である。モノを運ぶという目的は同じでも、生き物の馬を使うのとガソリンで動くマシンを走らせるのでは大違いである。馬の扱いに長け馬とともに生きてきた馬方と、トラックを運転するドライバーとでは、労働の質も違えば求められる資質も大きく異なる。
昨日までの馬方が、明日からは馬を捨ててトラックの運転手になることには無理がある。実際、機械化の波についていけず廃業・転業に追い込まれる業者も多数出た。しかし、小野運送店がそうであったように、多くの馬力運送業者は馬力とトラックの併用期間を経てトラック運送業へ、言い換えれば近代的な運送業へと脱皮していく。
小野運送店の場合、どのように主役交代が行われたのだろうか。
「私が入社したときはトラックが5台、馬もいました」と、存命の兄弟姉妹の中で最年長の為男は言う。為男が品川区役所勤務を経て入社したのは1963(昭和38)年であった。為男がさらに戦中の思い出として語ったのは、「最初の頃の空襲で馬が3頭、爆弾でやられました。ウチの隣で飛行機のタイヤをつくっていた明治ゴムが標的にされたのではないかと思います。入口の銀杏の木に吹き飛んだ馬の脚が引っかかっていた。そうこうするうちに建物が燃え出した。私が馬小屋につないでいた馬を放そうとすると、憲兵が来て駄目と言った。でも、このままじゃ焼け死んじゃうじゃないかと、かまわずつないでいた縄をほどきました。でも、空襲が終わると皆ちゃんと戻って来ました。馬は利口ですね。」
こうした証言にあるように、終戦までは間違いなく馬はいたようだ。
「戦後しばらくは仕事がなかった。馬は5~6頭いて、三輪車とトラックが1~2台でした。」(小野晃)
また、日本ペイントに就職した小野力(小野家6男、現・常勤顧問)は言う。
「私が日本ペイントに入社した1955(昭和30)年にはまだいたけれど、東京オリンピック(1964〈昭和39〉年)のときはもういなかった。恐らく1957 ・58(昭和32・33)年頃まででしょう。馬力をやめてから当社の近代化が始まりました。」
『「馬力」の運送史』には次のような記述がある。
「東京で、ほとんどの馬力運送は昭和30年代中頃には姿を消し、唯一残っていた江東区木場周辺で木材輸送に従事していた馬力運送が、やはり40年代後半に廃・転業し、都内でも馬力を見ることはできなくなった」と。
小野家と戦争の傷跡
小野運送店120年の歴史を振り返るとき、現役を引退した顧問・相談役の多くが図らずも口にしたのが戦争の記憶であった。その記憶は今も鮮明で色あせず、社業の運営のみならず、小野家の人々の人生にも大きな影を落としたことを示している。
二・二六事件(1936〈昭和11〉年)のとき、10歳の小学生だった為男は、陸軍の青年将校が起こしたクーデター未遂事件をリアルタイムで体験した。事件の発生を知り品川駅方向の八つ山まで事件を見に行った為男は、横浜方面から集結する兵隊に「坊やたち、危ないから帰んな」と諭された経験を持つ。
徴用されていた滝野川消防署が空襲で焼かれ、消防車が火だるまになって50mの火柱を吹き上げるのも見た。手ぬぐいも凍りつく真冬の軽井沢で、夜中に鉄砲を担いで演習をさせられた。戦後は占領軍がジープの上からバラまいたチョコレートを拾って食べ、そのあまりのうまさに負けて当たり前と思い知らされた。そんな経験を持つ為男が、最も悔み悲しむのが貞義の長男、自分には長兄に当たる小野倫義の戦死であった。
倫義は京都帝大卒の秀才。関東配電(今の東京電力)に入社するも半年後に徴兵され、北海道旭川で入隊。昔は長男は兵隊にとらない暗黙の了解があったが、それだけ戦局が厳しかったのだろう。予備士官になり北京に駐在。北支・山東郡白山縣における中国軍との戦いで戦死した。倫義の遺骨は、品川駅から一団の行列に囲まれて家に運ばれてきた。貞義の落胆ぶりは想像に余りある。
「一番出来のいいのが死んじまって、あとはクズばかり残っちまったとよく親父に言われた(苦笑)。」(小野晃)
晃は、戦時中は妹・義江、弟・修と一緒に創業者の生家のある愛知県碧海郡桜井町に疎開した。ここで、疎開児童ならではの苦労を味わったと言う。「一番食べたい盛りに、やはり疎開先への遠慮があってメシを十分食べることができない。地元の子どもたちには東京もんが来たといじめられた。あのときの苦しさ、つらさは今も忘れない。仕事でつらいことがあっても、疎開のときの苦労を思えばなんてことはないと思うね。」
力は、東京にいて空襲に見舞われた。「この辺りには焼夷弾ではなく爆弾が落ちた。私は近くのお寺の内側に屋根瓦でこさえた防空壕に飛び込んで無傷だったが、外側にいた人は皆やられました。」
為男が口ぐせのように言う言葉がある。それは“戦争は牛のかりんとう”──その心は「もう、コリゴリ」。どんな理由があっても二度と戦争は起こしてはならないと、為男は言う。