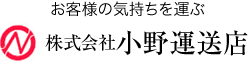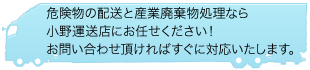創業者小野為吉
株式会社小野運送店の会社経営は、日本ペイント株式会社を抜きに語ることはできない。
創業以来、日本ペイントの塗料および原材料運送の専業会社として歩み続けており、事業所や営業所もすべて日本ペイントの工場や流通センターの運送需要に応じて展開してきた。日本ペイント専業の運送会社としてのスタンスは変わることなく、今日でも、関連会社を含めた荷扱い高は売上高の3割強を占める。
日本一の塗料メーカーである日本ペイントの発展が、塗料の運送を担う当社の成長を下支えし、日本ペイントの工場進出や事業拡大が当社の企業規模の拡大や収益向上をもたらしたのである。小野運送店120年の歴史は、日本ペイントとのパートナーシップの歴史といっても過言ではないだろう。
では、両社はいつ、どのような経緯で取引を始めるようになったのか。実は、創業者小野為吉が独立する前から日本ペイントとの接点はあった。
日本ペイントは、1881(明治14)年、東京の芝三田四国町(現・港区芝3丁目)に海軍艦船用調合ペイントの生産工場として設立された。当時の社名は光明社、創業者は茂木重次郎である。それまで輸入に頼ってきたペンキの国産化に成功した日本ペイントは、日本の近代化・工業化とともに急速に成長を遂げていった。
1896(明治29)年、日本ペイントは手狭になった工場を移転・新築することになった。その移転先が南品川、すなわち小野運送店本社の裏手に広がる土地だったのである。『日本ペイント百年史』によれば、分割所有していた田地の土地買収を終えたのが同年4月。敷地面積は約3,395坪であった。
「かつての品川は東海道第一の宿場ではあったが、漁業以外、何らの産業もなく、品川地区近代工場第1号の品川硝子製造所(約2,000坪=6,600㎡)も明治25年11月には解散していた」と、同書は当時の立地環境を伝えている。
為吉の英断
1896(明治29)年4月は、小野運送店の創業期(同年2月)と見事に合致する。小野運送店が偶然にも同時期に、しかも背中合わせの土地で開業したと考えるのは無理があり、ここはやはり、日本ペイントの新工場建設の情報を得た為吉が、近くの土地を買い付け、独立開業したと考えるのが自然であろう。
大学を卒業するとすぐに日本ペイントに就職し、日本ペイント販売株式会社の社長を長年務めた小野力は言う。「為吉は上京後、土木建築業の会社で馬方をやっていました。その会社は営膳関係で日本ペイントに入っていたと聞いています。おそらく為吉は馬力でペンキを運んだことがあったのでしょう。日本ペイントがここに来るという情報を入手し、それを機に為吉は独立して馬力運送業を起こした可能性が高いと思います。」
真実はどこにあるのか、為吉と日本ペイントとの間でどのような交渉が行われていたのか──。120年も前の出来事で確かめる術はない。しかし、創業者小野為吉が最初から日本ペイントの膨大な塗料輸送の需要に着目し、そこに大きな商機を見出して創業したことは間違いない。そして、その思惑どおり、小野運送店はその後一世紀以上にわたり日本ペイントとの緊密なパートナーシップを堅持し、専業の運送会社としての責務を果たしてきた。今日の小野運送店があるのは、為吉の先見性と英断によるところが大きいといえよう。
ゼロからのスタート
さて、交通統制と企業合同の暗く長いトンネルをくぐり抜け、ようやく本来の自主的な運送事業を行える日々がやってきた。
1945(昭和20)年8月、太平洋戦争が終結した。終戦まで米軍による延べ100回以上もの空襲を受けた東京は、文字通り焼け野原と化した。
東京空襲というと、深川地区などの下町を襲い、1日で十万人もの民間人が犠牲になった1945年3月10日の東京大空襲が有名だが、前章でも触れたように、軍需工場などが集中していた品川・荏原地区も爆撃の的となった。東京五大空襲の一つに数えられる同年5月24日の城南大空襲では、品川・荏原地区の大半が火に包まれ、多数の死傷者を出した。
そうした状況の中、小野運送店はかろうじて戦禍から免れ、幸いなことに、小野家から死傷者が出ることはなかった。しかし、戦前・戦中と国の統制下に置かれた運送業はほとんど活力を失っていた。馬力運送業として半世紀もの歴史を重ね、為吉・貞義の2代で地域有数の馬力屋に成長した小野運送店も、戦後はゼロからのスタートを余儀なくされたのである。小野晃が終戦当時を語る。
「戦後しばらくは仕事がなかったね。私の記憶では店には馬が5~6頭いて、三輪車とトラックがそれぞれ1~2台あったろうか。終戦から間もないので、頼みの綱の日本ペイントからの仕事もそんなになかった。その代わり、戦後復興で建築需要が少しずつ出てきて、材木の運搬でしのいでいたようだ。」
近隣の材木業者であろう。アサキヤ材木、ハギワラ材木といった荷主の名前が出た。
「それこそ5~6mあろうかという角材・板材を担いで建築現場に運んだ。ペンキ缶とは勝手が違って最初はきつかった。重たいし、肩は痛いし、腫れてしまうし。それでも次第にコツを覚え、うまく拍子をとってスイスイ運べるようになった。その頃になると馬ではなくトラック、といっても活躍していたのはまだ三輪車だった。」
何かあれば必ずお役に
国力を総動員した後の敗戦に、日本の産業経済は壊滅的な打撃を受け、ほとんど機能停止の状況にあった。
1881(明治14)年、協同組合光明社として創業以来、日本の塗料工業を牽引してきた日本ペイントは、昭和の初期にはすでに大企業の仲間入りをしていた。日本国内にとどまらず外地にも生産・販売拠点を拡大し、満州、北支、台湾に現地法人を展開していた。しかし、敗戦によってこれらの海外資産をすべて失った。また、国内でも大阪工場が焼失し、惨憺たる状況にあった。
しかし幸いなことに、当社と敷地を接する東京工場は無事だった。『日本ペイント百年史』に終戦直後の状況が記されている。
「東京工場は幸いにも戦災を免れたが、当時資材のひっ迫は甚だしく、生産継続のためには原料の手当てが必要であった。関係者は終戦とともに原料入手に奔走したが、隣の三共製薬株式会社に酸性白土があり、明治ゴム株式会社に亜鉛華があることが判った。ともに終戦直後のことで両社の生産再開に不必要なため交渉の結果、購入に成功した。しかし、大量の重量物資を輸送するための自動車などがなかったので、まず、リヤカーにより一日数十回往復して、自工場に運び込んだ。」
製品をつくるのに必要な原材料さえ底をつき、四苦八苦している状況が伝わってくる。この物資輸送に小野運送店が関わったかどうかは定かではないが、終戦時に残っていた数頭の馬が工場間輸送に貢献したとしても不思議はない。何かあれば必ずお役に立つ──それが、自他共に日本ペイント専業と認める小野運送店の一貫した姿勢であった。
「日本ペイントの株主総会が品川であると、必ず小野運送店の若い衆がハッピを着て会場の警護に当たったという話を、子どもの頃聞きました。荷主と下請けという上下関係はもちろんありましたが、それを超えた非常に親密な関係があったように思う。お隣でもあるし、小野運送店の人間は日本ペイントと“一心同体”という感覚を持っていたと思います。」(小野力)
日本ペイントがこうした状況では、戦前のような安定した仕事量を望むべくもない。一方で、終戦を境に、陸上輸送の主力はそれまでの馬力からトラックに、堰を切ったように移行していった。仕事量の激減、馬力運送の衰退、これに終戦直後の混乱が重なって、昭和20年代半ばくらい(1950年前後)までの会社の切り盛りは困難を極めた。
「日本ペイント自体もそんなに仕事がなく、材木運送の仕事で何とか食いつないでいくような状況だった。これは何も運送業に限らず、あらゆる産業・企業が同様の環境にあったと思う。それでも、終戦から少し経つと、住む場所だけは確保しようと住宅建築需要があちこちで生まれた。それまでペンキ缶ばかり運んでいたのが、この時期はいろんなものを運んだ。一番きつかったのはビールですね。木枠の箱に詰まったビール瓶を倉庫のかなり奥まで運ぶ、これがすごく堪えました。」(小野晃)
戦後復興の兆し
幸いなことに、塗料以外の貨物を運ぶ日々は半年と続かなかった。戦後の復興が始まるとともに塗料需要は復活し、日本ペイントの塗料製造は急速に拡大していく。
およそ塗料を必要としない産業はない。金属やプラスチックなどの表面に塗って素材を保護し、サビやカビを防ぐとともに、ものの見た目を美しくし、周囲に美しい景観をつくり出す、といった機能を付加するのが塗料の役割である。とりわけ、自動車・機械・電化製品などの製造業、橋梁・ビル・住宅などの建設工業においては不可欠だ。塗料工業を蘇生させたのは皮肉にも、日本の占領政策を指揮した米国進駐軍であった。
「終戦直後、進駐軍から大量の塗料の需要があり、その納入が優先されたため、当時国内に備蓄されていた原料を使用して、昭和21年にはその63%、22年には44%が進駐軍需要にあてられた。」(日本ペイント百年史)
進駐軍向け塗料製造の生産拠点となったのが、唯一焼失を免れた東京工場であった。国鉄(現・JR東日本)大井工場を中心に製造された進駐軍専用車両の使用塗料を供給するなど、東京工場は多忙を極めたと記述されている。
こうした日本ペイントの戦後復興の波に乗り、小野運送店の馬力運送の荷車、リヤカー、3輪車などの軽車両は再びペンキ缶で満たされるようになった。
1950(昭和25)年に「品川優申会」の会員になっている。優申会はその名の通り、優良な税務申告を行った企業でなければ会員になれない。終戦から5年、この頃には経営状況は改善され、馬力運送からトラック輸送への転換の足掛かりをつかんでいた。
日本ペイントとともに成長
1950年6月に勃発した朝鮮戦争は、日本の戦後復興に拍車を掛けた。韓国軍支援のために出動した米軍の発注による朝鮮戦争特需は塗料にも及び、日本ペイントの業績はこれをバネに一気に拡大基調に入っていく。
朝鮮戦争は3年ほどで休戦したが、弾みのついた日本経済は昭和30年代に入ると高度経済成長期に突入。鉄鋼、造船、機械、自動車などの重工業時代の幕開けによって塗料需要は拡大の一途をたどっていった。
日本塗料工業会30年史によれば、1956(昭和31)年の塗料生産量は19万6,362トン。これが東京オリンピック翌年の1965(昭和40)年には3倍強の64万トンに拡大している。日本ペイント百年史では、1951(昭和26)年から1965(昭和40)年までの約15年間を、会社が大きく前進した「進展期」に位置付けている。
日本ペイントとともに歩んできた小野運送店も、毎年、前年度の実績を大きくクリアする安定した受注に支えられ、売上高を確実に増やしていった。
もっともこの時期、高度経済成長の只中にあった日本企業のほとんどが業績を伸ばしている。ただ、小野運送店の場合は売上高という“量”の拡大にとどまることなく、“質”の転換が同時に図られたことに着目したい。質の転換、それはすなわち小野家による家内工業的な運送業から株式会社小野運送店への脱皮であり、馬力運送から近代的なトラック運送への進化を意味する。
馬力運送からの脱皮
「死んだ家内は、結婚する前は私と同じ品川区役所に勤務していて、助役の秘書をやっていた。その家内が図らずも言っていました。小野家の前の通りを通ると馬の匂いがひどくてイヤで、わざわざ第一国道の方へ遠回りして通勤したと。われわれは慣れっこになっているから気にならなかったけれど、ご近所には迷惑をかけたかもしれませんね。」(小野為男)
前近代的な稼業といわれた馬力運送。たくさんの馬を飼えば糞尿や飼料となる飼葉など、昔ながらの農家の匂いが周囲に立ち込める。また、運送中にも馬特有の臭気を発したり糞で道路を汚すなど、馬力運送は公衆衛生面に大きな問題を抱えていた。
ましてや南品川といえば、東京から直線距離10kmという都心である。「東京のど真ん中にこんな農家があることにびっくりした」とトシが語ったように、小野家は、戦前はさておき戦後は周囲の環境にそぐわない異質な存在であったろう。馬という生き物を手段とする馬力運送業は、環境に与える影響ひとつとっても衰退する運命にあった。
そこに、自動車という革新的な代替輸送手段が登場した。昭和20年代後半になると、三輪車を中心とした小型トラックの価格が安くなり、小型トラックは馬はもちろんリヤカーや大八車などを一掃していった。前述したように、東京では昭和30年代になるとほとんどの馬力運送業者は姿を消した。
小野運送店も、三輪トラックとの併用時期を経て、1957・58(昭和32・33)年頃には馬力から脱却したと考えられる。輸送手段の機械化に対応できずに廃業・転業した業者も少なくなかった中、スムーズに時代の流れに乗れたといえるだろう。
日本ペイントに土地を売却
そこにはおそらく、2代目小野貞義の進取の気性もあったのだろう。兵役においては騎兵隊に所属、馬の扱いを熟知し仕事を離れても馬をこよなく愛した貞義であったが、創業者の為吉同様、事業家として先を読む眼に秀でていた。いずれこの日が来ることを、かなり早い時期から察知していたに違いない。
それ以前に、日本ペイントという大企業の専業者としての自覚と責任が、旧態依然とした馬力運送業からの脱却を促した。進駐軍から平和産業とみなされた塗料工業が、この先飛躍的に伸びていくのは疑う余地もないことだ。運送需要も桁違いに伸びていくだろうし、もはや生き物を使った輸送の時代ではない。馬の代わりにトラックを、馬方の代わりに優秀なドライバーを雇い、近代的な運送事業者に生まれ変わらなければばならないという使命感が強く働いていたに違いない。
とはいえ、近代的運送業への転換を図るには資金力が必要だ。トラックの購入費、ガソリン代、車両のメンテナンス費用などが新たに発生する。小野運送店には相応の内部留保があったが、それでもまだ十分な設備投資を行うには足りなかった。
貞義はここで一つの勝負に出た。小野家の所有する土地で、日本ペイントに隣接する部分を同社に売却し、それをこうした設備投資資金に充てたのである。
この土地売却にはもう一つの意味があった。小野力が言う。
「日本ペイントの専業者はウチだけでなく、もう1社、K運送という競争相手がいました。そこはトラックをたくさん持っている関係でかなり優位に立っていた。表通りへの動線に当たる大事な土地を日本ペイントに売ることで得意先の便宜を図ると同時に、そのお金でトラックを購入して運送能力を質量ともに底上げする。実際、これによって劣勢を挽回したと聞いています」
貞義の戦略は見事に当たった。売却した土地は今の日本ペイントの東門に当たる部分で、トラックの出入りに欠かせない部分である。これにより日本ペイントとの距離はさらに縮まり、専業体制をさらに揺るぎないものとすることができた。為男が言う。
「親父は小学校しか出ていなかったけれど、非常に頭の働く人でした。終戦で、これからは兵隊さんがたくさん帰ってくるから地価が上がると言い、家の周囲の土地をどんどん買い足していった。日本ペイントに売ったのはそういう土地で、それまでは貸していたんです。」
個性の異なる息子たち
為吉からバトンを引き継いだのは1919(大正8)年。昭和30年代に入るころには、貞義の社長在任期間は40年近くに達しようとしていた。年齢も60歳を超えており、当時の男性の平均寿命は65歳前後であったから、十分に老境を迎えていた。後継者を誰にするかで悩んだ節がある。
貞義は先妻との間に3人、後妻との間に5人の男子をもうけている。戦死した長男・倫義を除くと、上から昌邦、為男、力、晃、修、倫義、八郎の順である。事業家の祖父・父の血を皆が受け継いでいるものの、当然のことながらその気性や適性、人となりはまちまちであった。
実質的長男の昌邦は大学を卒業すると日本通運に入社した。物流業界トップの企業で経験を積ませ、いずれは社長にという青写真が描かれていたと思われる。しかし、頭脳明晰かつリーダーシップを兼ね備えた昌邦は、入社すると本業よりも労働組合運動に傾倒。すぐに頭角を現し、日通労組の副委員長となり活動家として勇名を馳せた。
為男(1925〈大正14年〉生まれ)は子どものころから体が大きく、腕っぷしの強いやんちゃ坊主だった。小学校に入ると、国技ならぬ小野家の“家技”ともいうべき剣道に熱中し、品川区の大会で優勝したこともある。
「京都帝大剣道部の主将、剣道5段の戦死した長男・倫義が私の憧れだった。実は、親父の貞義も剣道の熟達者で範士の称号を持っていた。剣道一家なんです。高校を卒業して日本大学政治学科に進み、私も大学で剣道をやろうとしたら、20歳で終戦です。マッカーサーが入ってきて、柔道はいいが人斬りにつながる剣道は許さぬと。これには参りましたね」と、為男は当時を述懐する。大学を卒業すると家業とは距離を置き、品川区役所に勤務し税務を担当した。
力(1931・昭和6年生まれ)は温厚な性格の持ち主で、勤勉で実務派タイプの人間である。大学を卒業すると、就職難の時代に日本ペイントに入社した。同期入社は本人も含めて3人という超難関だったという。その後、製販分離して誕生した日本ペイント販売の取締役営業部長などの要職を歴任し、1979(昭和54)年に52歳の若さで同社社長に就任した。そして、1995(平成7)年に定年退職するまで16年間社長を務めた。力はいう。「家が運送業だからとか、親の会社の大得意だからという意識はほとんどなかった。もちろん、コネなど通用する余地はない。実力で入社したと思っております。」
晃(1935〈昭和10年〉生まれ)は、子どもの頃から家業を手伝い、休みのときにはトラックに同乗するなど運送業の現場を経験してきた。大学を卒業すると寄り道することなく、そのまま小野運送店に入った。その際、同時に弟・修、妹・義江も入社した(その後、弟・八郎、為男の長男・善康、次男・正彦、修の長男・竜士、倫義が入社)。1958(昭和33)年に入社し、65歳で退職するまでずっと現場に身を置き、率先して危険物・毒物などの免許を取り、労務管理や人材の育成に尽力した。
「子どものころから上の2人と違い、ことあるごとに家業を手伝わされていたから、ごく自然な流れでした。糖尿病を患わなければ、私がそのまま親父を継いでいた可能性が高いと思います。」(小野晃)
また、晃には以下の信念がある。
「運送業にとって、一番大切なことは事故撲滅である。そのために以下の5つが重要である。①運転手の自己管理(体調管理、深酒・喫煙をしない)、②スピードを出さない、③何事にも譲る心、他の車に道を譲る(ワキから入ってくる車に道を譲る)、④運転免許証のほかに、危険物免許証、毒劇物免許証などの取得、⑤全社従業員の安全に対する熱意→スローガンにある啓蒙など。そして、小野運送店のモットーは、社長をはじめ、全社員一丸となって、小野運送店発展のために努力することである。」
3代目・小野慶十
最終的に、貞義が代表の座を退いたのは1970(昭和45)年のことであった。社長在位は実に51年間。大正から昭和へ、太平洋戦争の混乱とその後の高度経済成長期も通じ、半世紀にわたり貞義は小野運送店の手綱を握り続けた。為吉が敷いたレールの上をただ走るのではなく、小野家の稼業を、その後100年間走り続けられる事業に育て上げた。貞義が中興の祖といわれるゆえんである。
1970(昭和45)年、新社長が就任した。3代目社長の白羽の矢が立てられたのは貞義の弟で、為吉にとっては貞義と同じ甥っ子にあたる慶十であった。
小野慶十は、実業の世界で成功を収めた兄の貞義とは対照的に、若いころから政治の世界を志した。戦時中は品川区の区議会議員を務め、戦後は東京の都議会議員を5期にわたり務めている。政財界に顔が広く、3代目社長になってからも、社長業よりもどちらかというと政治家としての活動に力を入れていたという。実際、社長在位期間は3年間と短かった。
「叔父のところには毛色の変わったいろんな人が入れ替わり立ち替わり訪ねてきて、実際の社長業は私がほとんどやっていた。4年に1度の選挙の時期がくると大変で、われわれも応援に駆り出されて大変だったのを覚えている」(小野為男)
このように、個性的な男子を輩出した小野家。後継者の人材には事欠かなかったが、大家族ゆえの軋轢や兄弟間の葛藤もあったと推測される。家族経営のリスクももちろん内在しているが、それをはるかに上回る結束力と小野家ならではのエネルギーで、小野運送店はさらなる飛躍の時期を迎えていく。